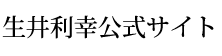トマス・アクィナス著、『神学大全』(Summa theologiae)における「人間の尊厳」
中世イタリアのスコラ学最大の神学者・哲学者、トマス・アクィナス(Thomas Aquinas, 1225-1274)は、同時に、ドミニコ会士、教会博士(doctor ecclesiae)としても知られている人物である。言うまでもなく、トマスの代表的著作は、所謂、『神学大全』(Summa theologiae)である。12世紀から13世紀にわたって多数のスコラ神学者(オセールのギレルムス、ヘイルズのアレクサンデルなど)によって『神学大全』(Summa theologiae)が執筆されたが、その中でもトマス・アクィナスの著作が最も評価が高いと明言できる。
トマスの『神学大全』は三部から成り、第一部の執筆は1266年、彼が41歳の時である。1274年、トマスは第三部の最終部分を仕上げようとしている時期に他界したが、ドミニコ会における彼の友人、ピペルノのレギナルドスが、トマスの『命題集注解』(Scriptum super libros sententiarum)から該当する部分を抜粋・編纂して完成させるに至った。
トマスは、「人間の生命」、そして「人間の尊厳・尊厳性」の概念について詳細に論じている。トマスが用いるラテン語のdignitasは、「尊厳」の他、「威厳」「品位」「重要性」「優位性」「威厳」「身分」「役割」などを意味するものだ。
トマスは、以下の如く述べる。即ち、「生命は、神によって人間に授けられた何らかの賜物であり、殺し、かつ生かすところの彼方の権能の下にある」と。これは、トマスが『神学大全』において述べた「人間の生命」についての大前提として捉えることができる。
キリスト教においては、旧約聖書以来、生命は神からの賜物であり、神と呼ばれる存在は、「命の道」を提供する「生ける水の泉」であり、且つ、「命の水」である。そして、新約聖書においては、神は、「豊かな命を与える者」であり、「生命を与える霊」であると述べられている。中世の神学者は、「神」や「生命」について、それらのすべてを聖書の立場から立脚して論じるのが通常であったが、トマスの場合はそうではなかった。
トマスは、それらを探究するにあたり、古代ギリシアの哲学者、アリストテレスから強い影響を受けた。トマスは、アリストテレスの著書『政治学』(Politica)の一節を引用。『神学大全』においてこの世に存在する生命・いのちの価値について格付けを行った。
トマスは、『神学大全』において次の如く述べる、・・・即ち、生命の”階級”は、(1)低位に位置する存在は「生きているもの」(vivum)、(2)中間に位置する存在は「動物」(animal)、(3)上位に位置するものは「人間」(homo)であり、(4)これらの最上位にあるものが命への導き手としての「主」である、と。
トマスは、植物のように生きているところのものは、一般的にはすべての動物のためにあり、そして動物たちは人間のためにあると述べる。したがって、もし、人間が植物を動物に役立たせるために使用し、動物を人間に役立たせるために使用したとしても、それは決して不当なことではない。この考え方は、アリストテレスが『政治学』第1巻第8章で述べているところからしても明白である、と述べる。
トマスによると、植物を動物の使用に供するために、また、動物を人間の使用に供するために殺すことは、”神的な秩序づけ”そのものからして許されている。これは、事物の秩序においては、「不完全なものは、より完全なもののために存在する」という大前提から出発し、生成のプロセスにおいても、まず第一に植物のように(1)「生きているもの」があり、次に(2)「動物」、そして(3)「人間」が出現したのであるから、本来、植物は動物のためにあり、動物は人間のためにあると解される。すべての人間は、所謂、”動物の一種”として捉えられる。そして、人間は、他の動物よりも上位に位置づけられている存在である。そうである理由は、人間には、理性によってなされる「『真理』についての認識能力」があるからである。
理性は、まさに「神の似像」(imago Dei)といえるもの。トマスは、「理性」と「知性」は、人間にあってはそれぞれ別の能力であると捉えることはできないとし、理性的被造物がそれ以外の被造物を越える所以のものは、まさに「知性」「精神」にあるとした。
非理性的な存在である動物や植物も、人間と同じように”神的な秩序づけ”によって維持されているのであるが、それらは「理性的生命」を持ってはいない。それらは、常に、他者を介して、「自然本性的な衝動」によって動かされているだけである。言うなれば、動物や植物は、<自然本性的な奴隷状態>にあるのであり、究極的には「人間の使用に供される宿命を背負っている」のである。
『神学大全』では、「人格の品位」「諸々の人格の重要性」「人格の威厳」「人格の重要性」という表現が用いられている。この「人格」という語は”persona”であり、「品位」「威厳」「重要性」という語は”dignitas”が用いられている。当初、トマスは、personaという語を、「神について適切に語られる」、あるいは「神に対して最高度に適合する」と定義づけをしていた。そして後に、何らかの”優越性”、つまり、dignitasの要素を有する人間(さらには、理性的本性を有するすべて固体)に対してpersonaと呼ぶようになった。
トマスは、理性的な本性において自在するところのものは「非常な優位」を持つ、と説く。ここにおいて、トマスは、人間を、”理性的なもの”と捉えていたことがうかがえる。
非常な優位・尊厳性を保持する者は、「理性」を巧みに作用させ、認識したり知的に捉えることができる限りにおいては、そうした存在者を人間として解することができる。トマスにおいては、非常な優位・尊厳性のある人間とは、いわゆる「理性的存在者」のみを指す。罪人や悪人などの非理性的動物としての人間は、確かに<ヒト>ではあるが、そうした者たちを「尊厳」の所有者とみなすことはできないとした。
注)
トマス・アクィナス(Thomas Aquinas)は、1225年、ナポリ郊外のアクィノ領・ロッカセッカ城で生まれ、5歳の時、モンテ・カッシーノのベネディクト会修道院に入り、後にナポリ大学で学んだ。1244年にドミニコ会に入会し、45年にパリでアルベルトス・マグヌスに師事する。1256年、神学教授資格を授与され、同年、第1回パリ大学神学部教授に就任。72年、イタリアに戻りナポリ大学などで教えていたが、2年後の74年に没した。